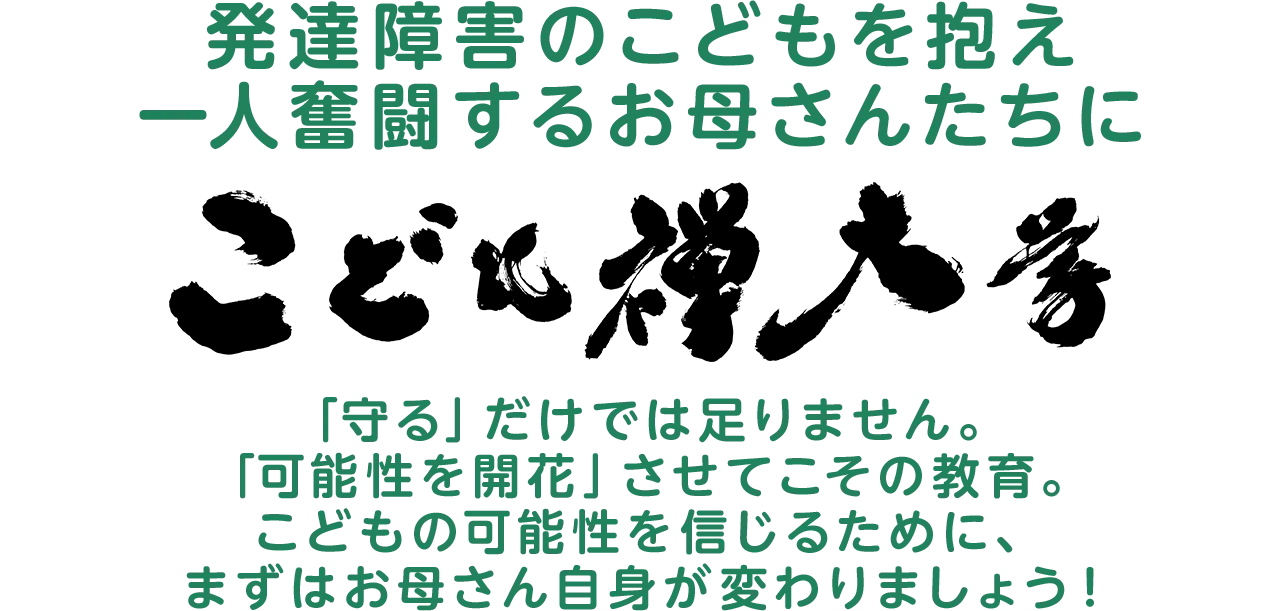
「こども禅大学」の始まり
お寺でのこども向け教育活動は2015年、東京は港区三田の龍源寺さんから始まりました。
龍源寺さんは、福沢諭吉が啓蒙思想を広めたお寺です。
このような歴史あるお寺で、「こども禅大学」は開幕しました。
三つの人間教育の根本
自分自身が発達障害のこどもの親になって気づかされた、三つの課題があります。
「可能性」
「自由」
「創造」
この活動を始めるにあたっておよそ100人の同じ境遇のお母さんたちの悩みや不安に触れてきました。発達障害が社会の未来を占う大きな課題となるまでに、声なき声が出ていたのは事実です。しかしその声は無視されてきました。この障害を知らないまま、前時代的な教育観によって育てられた30代40代の人たちにも会いました。紋切り型の頑固な先入観は、結果として我が子を自己卑下するばかりの大人にさせてしまいます。
しかし今、発達障害という診断によって既定路線から外れてしまうこどもたちが身を以て、私たち大人に克服すべきこの三つの課題を示しています。
可能性は信じるからこそ認められるのです。
学びは常に自由なのです。
既存の枠に合わせ「ない」から創造になるのです。
これら三つの人間教育の根本は、既存の教育システムではなおざりにされてきました。このシステムの弊害が、「障害」という形で露わになったのです。
既存の教育環境に馴染めないこどもたちの感性こそ、未来への道標となるでしょう。
こども禅大学の主眼は、目先の損得優先の私塾とは真逆です。この活動の利益は金銭ではありません。発達障害のこどもを抱え、一人で奮闘するお母さんたちが、悩みに素直になる場です。悩みや苦しみを共有し、教育や禅や哲学の専門家から知恵を授けられ、健全でリラックスした子育てができるようになる「お母さん自身の気づきの場」です。
「可能性とは?」「自由とは?」「創造とは?」
可能性とは希望です。そして希望は生きることです。生きることは様々な縁に支えられ、そして様々な縁を支えることです。ともに支えあえる人たちが「可能性」の拠り所となるのです。親として抱えてしまう悩みの数々こそ可能性の証です。
「不自由なき自由」思考は自分自身を苦しめます。そして「不自由なき自由」思考者たちが共生を阻み、未来を貧しくしています。
成功しか眼中にない安定資本一択型の人間はこの道理にはなかなか気づけません。しかし、障害を抱えるこどもとその親、そして支援者たちは、肌と心でこの道理を感じ取るでしょう。これからそれを、発達障害のこどもたちが証明する時代になるでしょう。「こども禅大学」活動は、時代を先駆けます。
自由なき不自由は非情で残酷です。またその逆、不自由なき自由こそ愚かで哀れです。「不自由であるからこそ自由である」、この哲理を発達障害のこども達が教えてくれるでしょう。
「障害があるままでいい。失敗してもいい。道を外れてもマイペースで歩けばいい」と素直になることで、流れが好転していきます。その先に創造が見えてきます。
「障害」なるものはしばしば忌避されるものです。障害は順風満帆だったキャリアを壊してしまうもの、なんて考えられているようですが、ずいぶん息苦しい縄で自分を縛りつけていますね。彼らに創造など不可能でしょう。
創造は制限や不自由、そして障害の内に芽生えるのです。それをお母さんは信じてください。
なぜ「禅」の「大学」なのか?
禅から何を連想されるでしょう?
坐禅でしょうか。あるいは柔道や空手などの武道でしょうか。あるいは茶道や華道でしょうか。そのどれにも共通する教えが「自由」です。
「自由=障害がないこと」と理解されているかもしれません。しかし、本来の自由はそれとは別次元であることを、禅は教えてくれます。
こども禅大学は、「障害はあるがままに、自由な心で、自由なペースで、自由な好奇心で学べる」場所です。
禅では「学び」の基本も説かれています。それを証する「活発発地」という言葉があります。こどもたちは本来、フレッシュで活発です。その活力があり過ぎて、社会のルールや暗黙の了解を壊してしまうのが、私たちのこどもですよね?
過ぎていてもいいじゃないですか!それこそ自由なエネルギーの証拠です!
しかし、「大人の事情の勉強」「生産・効率主義的発想」によって、このようなフレッシュな感性を閉ざしてしまうこどもたちが出ています。
こどもが自然に授かったら力を、評価や生産性から解放し、そして開花させるための考え方や心のあり方を身につけられるでしょう。
「大学」はそもそも、自由な学びの場。将来の安定のために入学するところではありません。
この活動を通してお母さんたちは、失敗に苛立たず落ち込まず、失敗にワクワクする力を身に着けるでしょう。そして世の中には多種多様な仕事があることを知り、数々の失敗談や工夫や知恵を身近に感じ、学力だけでは測れない未来があることを実感できるでしょう。
なぜお寺なのか?
教育現場は学校だけではありません。お寺の役目は法事だけではありません。そもそも「寺と教育」は、江戸時代には切っても切れないものでした。明治という群雄割拠の世界で日本がここまで発展できたのも、寺子屋での教育が貢献したからです。
お寺では誰もが自分自身に素直になってしまいます。
「できない」自分であることは恥にはなりません。むしろ「できる」アピールをすることが、恥。
お寺では、「人生は思い通りにならない」ことを、身をもって学ぶことができるでしょう。そして、「できなくてもなんとかなる」ことを実感できるでしょう。
画一的な評価や、キャリアのプレッシャーから早々に離脱できたことは、むしろ幸いなのです。不安や葛藤の裏側には、このような幸運が隠れているのです。お母さん自身が自由になれば、こどもも自由自在に成長していくでしょう。マイペースでいいのです。できないことがたくさんあってもいいのです。
お母さんが繋がりあい学びあう場
「こども禅大学」はお母さんたちの覚醒の場です。そしてこどもの可能性を見つけていく場です。
この場には、孤立したまま奮闘していたお母さんたちが集まります。仲間たちの不安や悩みに気づき、共有し、そして自分自身の思い込みを知ることで、余計な負荷を降ろせるようになります。そしてこどもたちと素直に向きあえるようになります。
素直にならなければ可能性は隠れたまま、いずれ枯れ果ててしまうでしょう。こどもの可能性を信じましょう。学びは常に自由です。そして共にこどもたちの未来を創造していきましょう。
